今年、ご家族に不幸があったときは、喪中ということでその年の年賀状は出しません。
喪中の期間とは、近親者が亡くなった日から1年間を喪中とするのが一般的です。その中で、四十九日法要までは忌中として、より厳格に身を慎む期間とされています。
喪中はがきの文例
「喪中につき新年のご挨拶は失礼させていただきます
本年○月○日 ○○が ○○歳にて永眠しました
ここに平素のご厚情を深謝いたしますとともに
明年も変わらぬご厚詮のほどお願い申し上げます
令和○年11月」
あとは、ご自身でアレンジされるのもいいと思います。
だれが何時何歳でなくなったのか、故人が生前にお世話になったお礼と挨拶を書きます。
喪中の挨拶はがきは、いつごろ出せばいいのでしょうか
これは、11月中には相手に届くように出すのがいいです。
年賀状のあて名を書くのは12月に入ってからだと思いますので、その前に届くように出すのが相手にとって負担になりません。
あまり早く出し過ぎても、届いたはがきをどこに置いたかわからなくなることがありますから、11月中に届くと、もらった方の管理もしやすくなりますよね。
年末になって急に不幸があったときは
12月半ばも過ぎて、自分も年賀状を書いてしまったし、もう皆さんも年賀状を書いてしまったころに不幸があったときはどうすればいいのでしょうか。
私は欠礼挨拶を出しました。でも、送った相手の方が年賀状を出してしまったことをとても恐縮していました。
しまったーと思いました。
こんな時はあえて喪中はがきを出さなくていいのです。
喪中の方は年賀状も出しません。
そして、年明けの正月気分が抜ける松の内(1月7日)が過ぎた1月8日ごろ、「寒中お見舞い」はがきを出します。その文面に、昨年末に喪中となったので年賀状を欠礼したことを簡単にわびます。
文例
「寒中お見舞い申し上げます
寒さはこれからが本番ですが、皆様にはお変わりございませんか
〇〇〇〇(続き柄)の喪中のため年始のご挨拶を差し控え失礼いたしました
こちらは風邪もひかず皆元気で過ごしています
今年もなにとぞよろしくお願い申し上げます
令和〇年 1月〇日」
これで充分。
もらった相手方に必要以上に負担をかけてはいけません。
12月はじめごろまでに喪中はがきが相手方に届くのなら出せばいいと思いますが、それ以後なら出さない方がいいでしょう。
忙しい師走。そして新年を迎えようとしている時期に、あまり気が利いたものではありません。
年賀状を欠礼するのはこちらの都合であって、相手方には何の責任もないのですから。
喪中はがきは、喪中の人が年賀状を欠礼することをお詫びするものなのです。
相手側に「年賀状を出さないでね」という案内ではないのです。
だから、喪中はがき来てたの忘れて年賀状を送っちゃったー。これは全然問題ないのです。
だって、喪中はがきが届けられた方に面倒なことを強いるのは、それこそ失礼でしょう。
でも、慣習的に喪中はがきをもらった方は年賀状を出さないように気を使います。
喪中はがきを受け取った側は
喪中はがきを受け取ったときは、その相手方には年賀状を出すのを控えます。
ただ、相手が親しい人だったり、近況を聞いたり励ましたりしたい場合は、年が明けて松の内が明ける1月8日以降に届くように「寒中お見舞い」を出すといいと思います。
郵便局は1月5日までに投かんした年賀はがきは松の内(1月7日)までに配達しますが、普通はがきの寒中お見舞いはがきは三が日が過ぎたころに出せばちょうどいいかと思います。
マナーとしては、寒中お見舞いは、寒の入りである1月6日ごろから、大寒である立春の前日(2月2日ごろ)までに出すものとされているので参考までに。
寒中お見舞いの文例は次のページをご覧ください。

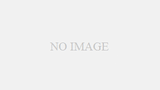
コメント